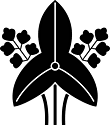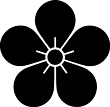文様としては古く唐時代に用いられわが国へ伝来しました。木瓜とも記しますので胡瓜の切り口を連想しますが、本当は地上の鳥の巣を表現したものとされています。神社の御簾の帽額(もこう)に多く使われた文様であったので、もっこうと呼ばれるようになったと云います。
鳥の巣は子孫繁栄を意味し、神社で用いる御簾は吉祥であるということから、めでたい紋とされ、織田信長を代表として家紋とした武家は多くあります。その幾何学的で図案化しやすい絵柄からも分かるように、大変バリエーションの多い紋です。
常陸の多賀谷氏、清和源氏流の田中氏、藤原氏流の大村氏、佐沼氏、苅部氏、栃渕氏、菌田氏、石田氏、箕勾氏、新見氏などが用いたとされています。
※この項「木瓜」参照
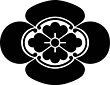 木瓜 |
 五瓜に唐花 |
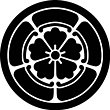 丸に五瓜に唐花 |
 織田木瓜 |
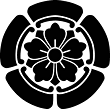 大村瓜 |
 五瓜に梅鉢 |
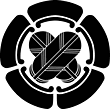 五瓜に違い鷹の羽 |
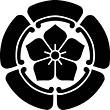 五瓜に桔梗 |
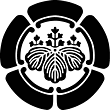 五瓜に五三桐 |
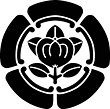 五瓜に橘 |
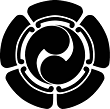 五瓜に二つ巴 |
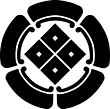 五瓜に四つ目 |
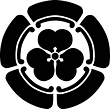 五瓜に片喰 |
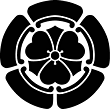 五瓜に剣片喰 |
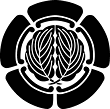 五瓜に抱き柏 |
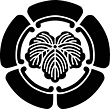 五瓜に蔦 |
 五瓜に三つ柏 |
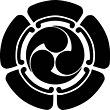 五瓜に三つ巴 |
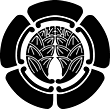 五瓜に抱き茗荷 |
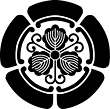 五瓜に蔓柏 |
 五瓜に違い矢 |
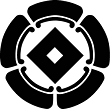 五瓜に隅立て一つ目 |
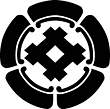 五瓜に井桁 |
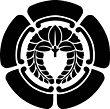 五瓜に下がり藤 |
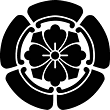 五瓜に四方剣花菱 |
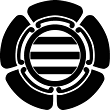 五瓜に丸に三引き |
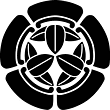 五瓜に九枚笹 |
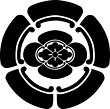 五瓜に木瓜 |
 五瓜に片手蔓柏 |
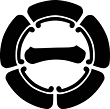 五瓜に一の字 |
 五瓜に立ち沢瀉 |
 五瓜に渡辺星 |
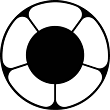 三井瓜 |
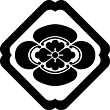 隅入り角に木瓜 |
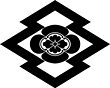 中陰松皮菱に木瓜 |
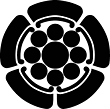 五瓜に九曜 |
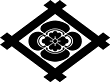 井桁に木瓜 |
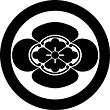 丸に木瓜 |
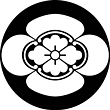 石持ち地抜き木瓜 |
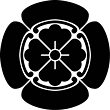 四方木瓜 |
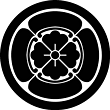 丸に四方木瓜 |
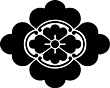 唐木瓜 |
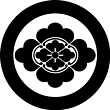 丸に唐木瓜 |
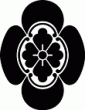 立ち木瓜 |
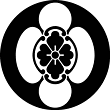 堀田木瓜 |
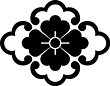 唐鐶木瓜 |
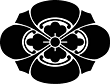 剣木瓜 |
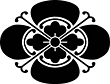 蔓木瓜 |
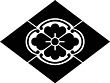 木瓜菱 |
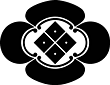 木瓜に四つ目 |
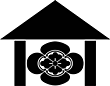 庵木瓜 |
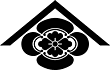 山形に木瓜 |
 木瓜に二つ引き |
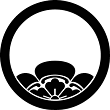 丸に覗き木瓜 |
 三つ盛り木瓜 |
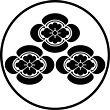 細輪に三つ盛り木瓜 |
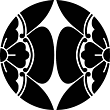 割り木瓜 |
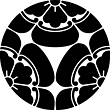 三つ割り木瓜 |
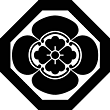 隅切り角に木瓜 |
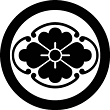 丸に鐶木瓜 |
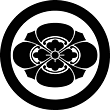 丸に剣木瓜 |
 丸に木瓜に五三桐 |
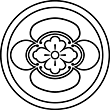 陰丸に陰木瓜 |
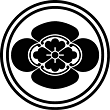 二重輪に木瓜 |
 四方木瓜に抱き茗荷 |
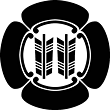 四方木瓜に並び矢 |
 丸に四方木瓜に剣片喰 |
 雪輪に木瓜 |
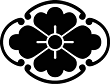 鐶木瓜 |
 瓜桐 |
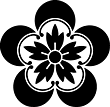 太田瓜 |
 相良瓜 |
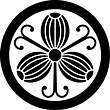 丸に三つ蔓瓜 |
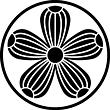 細輪に五つ瓜 |
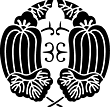 抱き瓜 |
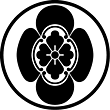 細輪に立ち木瓜 |
 木瓜巴 |
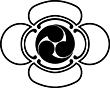 陰木瓜に三つ巴 |
 割り木瓜菱 |
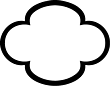 木瓜形 |
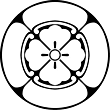 石持ち地抜き四方木瓜 |
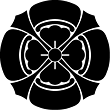 剣四方木瓜 |
 一重瓜に木瓜 |
 陰五瓜に唐花 |
 瓜の花 |
 瓜輪 |
 剣五瓜に唐花 |
 五瓜に六つ剣唐花 |
 三つ瓜に唐花 |
 柴村瓜 |
 鷹取瓜 |
 中陰五瓜に唐花 |
 唐五瓜に唐花 |
 二つ割り瓜 |
 米田瓜 |
 変わり瓜に三つ巴 |
 木村瓜 |
 六つ瓜に唐花 |