 器物紋
器物紋 錨|いかり
浅い海で船体をつなぎ止めるための重しが錨の役目です。元々は石や木を使っており「碇」の字を当てていたのですが、時代が下がって鉄製となりました。猫の爪のように引っ掻く形状ですので「錨」という字が生まれたそうです。面白いですね。船をつなぎ止める威力、形の力強さから紋章になったのでしょう。珍しい紋ですが、明治以降近代になってから、形が制定されたものもあり、けっこう形のバリエーションは豊富です。
 器物紋
器物紋 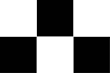 器物紋
器物紋 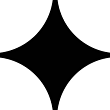 器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋 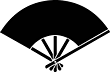 器物紋
器物紋 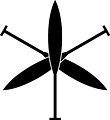 器物紋
器物紋 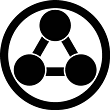 器物紋
器物紋  器物紋
器物紋 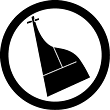 器物紋
器物紋 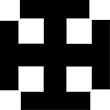 器物紋
器物紋 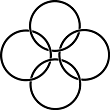 器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋 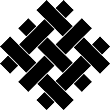 器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋 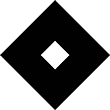 器物紋
器物紋 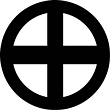 器物紋
器物紋  器物紋
器物紋 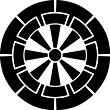 器物紋
器物紋 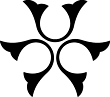 器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋 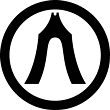 器物紋
器物紋 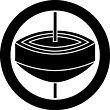 器物紋
器物紋 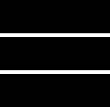 器物紋
器物紋 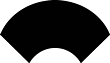 器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋 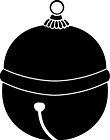 器物紋
器物紋  器物紋
器物紋  器物紋
器物紋 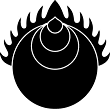 器物紋
器物紋 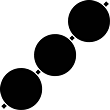 器物紋
器物紋 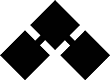 器物紋
器物紋  器物紋
器物紋