 自然紋
自然紋 稲妻|いなづま
稲光が豊作をもたらすとの信仰から、室町時代から家紋として使用されています。紋様は直線が繋がりながら曲折していく幾何学的模様で、古くから各種の器物や建築などに用いられています。稲妻紋は雷紋ともいい、色々なデザインパターンがあります。この紋はその特殊性から呪符のようなイメージがあり、ポピュラーな家紋ではありませんが、意匠的にはとても面白いですね。
 自然紋
自然紋 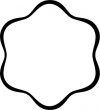 自然紋
自然紋  自然紋
自然紋  自然紋
自然紋  自然紋
自然紋 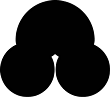 自然紋
自然紋 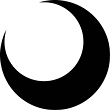 自然紋
自然紋 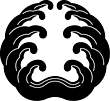 自然紋
自然紋 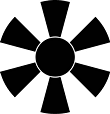 自然紋
自然紋 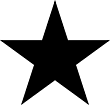 自然紋
自然紋  自然紋
自然紋  自然紋
自然紋 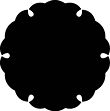 自然紋
自然紋